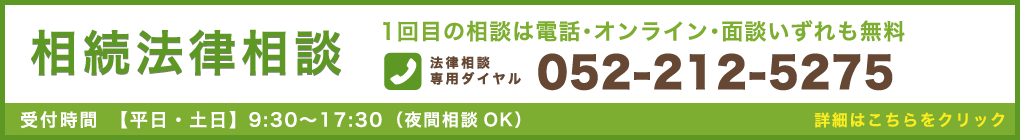相続放棄の手続は、原則として、自分が相続人となっていることが分かってから3か月以内に、家庭裁判所に申し立てることによってする必要があります(民法915条1項本文)。
では、この期間を経過してしまった場合には絶対に相続放棄はできないのでしょうか?
この点についての先例となっている裁判例を2つ紹介します。
1つ目は、最高裁昭和59年4月27日判決(民集38・6・698)です。
当該判例は、相続放棄の起算点について、「3か月以内に相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、そのように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識したときまたは通常これを認識しうべかりしときから起算するのが相当である。」旨判示しています。
2つ目は、東京高決平成12・12・7(家月53・7・124)です。
当該裁判例は、被相続人の遺言の内容から自らは被相続人の積極及び消極の財産を全く承継することがないと信じた場合には、「相当の理由」があるとして、相続放棄の申述受理の申立てを認めたものです。この裁判例は、遺言があっても、その内容から、上記最高裁の判例のいう「正当な理由」があると判断した事例です。
このように、3か月以内に相続放棄をしなかった(できなかった)ことについて、「相当の理由」があると認められれば、相続放棄が認められる場合もあるのです。
もっとも、「どのような場合に「相当な理由」があるか、ということは高度に専門的で、個々の事案・資料の有無等によって変わってくるため、弁護士に相談することを強くお勧めします。
「相当の理由」が認められるのはあくまで例外の話であるため、一定のハードルはありますが、相続を知った時から3か月が経過してしまっているから絶対に相続放棄はできないとあきらめるのではなく、お手持ちの資料をご持参のうえ、なるべく早く弁護士に相談しましょう。
名古屋藤が丘事務所弁護士 浅野 桂市
遺産分割協議をするにあたり,相続人のうち未成年者がいると「特別代理人」という制度を利用しなければならないケースがあります。
どのような場合に「特別代理人」を選任しなければならないかについて,整理したいと思います。
1 親権者も相続人となっている場合
例えば,夫が死亡して,相続人が妻とその子供(未成年者)であるケースです。
この場合には,妻は子供のために「特別代理人」の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。
なぜなら,妻の取り分が多くなれば子供の取り分が少なくなるため,親権者である妻と子供とは利害が対立する関係です(「利益相反」といいます)。民法826条1項は,親権者が子供の利益を害する結果にならないようにするため「特別代理人」の選任を必要と定めています。
2 親権者が相続人となっていない場合
例えば,元夫が死亡して,その子供が相続人となるケースです(元妻は相続人にはなりません)。
(1) 親権者を共通する未成年者が1人の場合
例えば,元妻が親権をもつ子供が1人であり,他の相続人が現妻だけのようなケースです。この場合には,「特別代理人」を選任する必要はありません。
元妻は,相続人ではないため,子供に代わって遺産分割協議をしても子供と利害が対立しないためです。
(2)親権者が共通する未成年者が複数の場合
例えば,元妻が親権をもつ子供が2人いるケースです。この場合には,「特別代理人」を選任する必要があります。
なぜなら,上の子供の取り分が多くなれば下の子供の取り分が少なくなるため,子供同士で利害が対立してしまうためです。
民法826条2項は,どちらか一方の子供の利益が害されないよう,親権者が代理できる子供を1人だけに制限しています。そのため,親権者として代理する子供(例えば,上の子供)以外の子供(下の子供)について「特別代理人」を選任しなければなりません。
ご自身が「特別代理人」を選任する必要のあるケースか,「特別代理人」の選任の方法が分からない場合には,一度弁護士にご相談してみてください。
刈谷事務所弁護士 丸山 浩平
このブログをお読みいただいている方の中には,現在,ご両親の介護をされている方も多くいらっしゃることと思います。そのような方々にとって,相続の問題は,決して遠い将来の問題ではないはずです。
当然,ご両親の介護には,介護費用の負担がつきものです。ご両親に預貯金がある場合,ここから介護費用を支出するということはとても自然なことですし,介護はご両親のために行っていることですので,その大変さは他の相続人らにもわかってほしいところです。
しかし,ご両親のためにやったことが,その死後,相続トラブルのきっかけとなってしまう残念なケースがあります。
例えば,ご両親に頼まれて,介護に関わる高額な物を継続的に購入したとします。その場合,ご両親の預金口座から現金を引き出して購入資金に充てたとしても,それはご本人の意思に基づいて,ご本人のために,ご本人の財産を使っているだけですので,法的に何の問題にもなりません。
ところが,それら使途が通帳に記録されるかというと,されませんよね。そうすると,特に疎遠で,介護の詳細も知らないような他の相続人にとっては,その通帳の記録は,親の預金口座から,ただひたすら使途の不明な金銭が引き出されているだけの履歴に見えてしまうかもしれません。
このような場合,本来あるはずのご両親の遺産が減っていることを理由に,他の相続人から,不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求をされることがあり得ます。その時,使途を証明するものが何もなければ,引き出したお金について自分が使ったわけでもないのにこれを返さなければならず,なぜ介護した私が・・・ということになってしまう可能性があるのです。
もちろん,このような場合は弁護士にご相談いただければ,真実を証明するために,できる限り協力させていただきます。しかし,ご家族の不要なトラブルを避けるためにも,現在介護されている皆様は,お金の使い道がご両親の意思に基づくことやその使途の詳細について,記録を取られたり,領収書を保存されたりして,将来に備えていただくことが大切なのです。
介護の大変さを一番よく知っているのは,介護されているご本人自身だと思います。もし,将来こんな紛争になってしまうのではないか,と心配されているのであれば,紛争になっていない今のうちに,一度弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
四日市事務所弁護士 西村 綾菜
名古屋丸の内本部事務所で執務しております,弁護士の中村です。今回は,相続の問題でご依頼いただくときなどに非常に大事な,弁護士のルールについてご紹介したいと思います。
例えば,被相続人Aさんの相続人が,配偶者のBさん,子がCさん,Dさん,Eさんだったとします。Aさんが遺した遺産の分け方について,BさんとCさん,Dさんの意見は一致しているけれども,Eさんだけ反対しているという状況で,Bさん,Cさん,Dさんが,Eさんを相手方として遺産分割協議の依頼をしたいと事務所にお越しいただくことがよくあります。
弁護士としては,皆さんのお力になりたい気持ちは山々なのですが,ここで気を付けないといけない弁護士のルールがあります。
具体的には,弁護士は,当事者の利益が相反している事件について職務を行ってはいけないというルールです(弁護士法や弁護士職務基本規程に定められています。)。複数人の間で,利益が反するような状況であるとき,弁護士として両方の味方をすることはできないというわけです。
先ほど挙げたような場合でも,このルールが大きな問題になります。
依頼を考えている現状では,Bさん,Cさん,Dさんは同じ意見で一致していることから,Bさん,Cさん,Dさんの間では利益相反の関係は生じていないと言えそうです。しかし,遺産分割の話合い・手続はなかなか一筋縄でいくものではなく,長期化することも多いため,進んでいく途中でDさんの考えが変わってくるということも起こり得ます。
ご依頼をいただいた弁護士としては,このように途中でBさん,Cさん,Dさんが対立することになった場合,すなわち利益相反状態が顕在化した場合,全員について代理をすることができなくなるため,辞任することになります。
このような,利益相反状態が顕在化してしまい,全員について辞任することになってしまうリスクがあるので,Bさん,Cさん,Dさんからご依頼をいただくことは可能ではありますが,このリスクについて十分にご理解いただく必要があります。
また,ご依頼いただく際には,この点について,利益相反顕在化による辞任のリスクがあること等記載した合意書を,弁護士との間で作成させていただいております。
上記のような遺産分割の問題でご依頼をいただく際は,このような弁護士のルールがあるということについて,ご承知おきいただければと思います。
浜松事務所弁護士 中村 展
こんにちは,弁護士の加藤耕輔です。
最近,相続関係の業務をしていて,不動産(老朽化建物,農地など)について相続人の誰もが取得を希望しないという事案に一定数,出会います。
そのような場合,通常,相続人は,順次相続放棄をしていき,最終的に相続人が不存在となり,「相続人が不要と考えた不動産が残る」という事態が生じます。
このとき,そのまま放置されてしまうこともあるのですが,相続人や被相続人に対する債権者が,『相続財産管理人』の選任を裁判所に申立て,裁判所が選定した弁護士が相続財産管理人として,「不要と考えられた不動産」を管理するということとなります。
相続財産管理人は,その他の相続財産の調査・債権者の整理・他に相続人がいないかの調査(申出催告)・特別縁故者への分与を申出があればとその対応,をする間に,「相続人が不要と判断した不動産」の換価を試みます。
ただし,相続人一同が不要と考えた不動産について,買い手がつくことはなかなか難しいことが少なくなく,最終段階までに,売却ができなければ,不動産のまま,国へ帰属させることとなります。
「国に帰属する」と,言うのは簡単ですが,実際に,国が引き継ぐ際には,「きれいな状態」で引き継ぎを希望するため(法的な根拠はないのではないかと思います。実務上の運用だと思います。),老朽建物がある場合には解体・土地測量・電気ガス水道の契約関係の調査等を行って所定の手続きに従って,名義変更を行うこととなり,特に建物解体が必要な場合は,高額になりがちな解体費用の予算組みなど慎重な対応が求められます。
国庫帰属を完了させるまでに,数年を要する事案は少なくなく(私も,数件保有しています),今後,都市への人口集中がより顕著になれば,郊外地域で同様の事案はどんどん増えていくことになると見ています。
私見ですが,国庫帰属になる場合でも少なくとも2年で終わるような,法改正なり,制度設計が必要ではないかと感じるところです。
津島事務所弁護士 加藤 耕輔